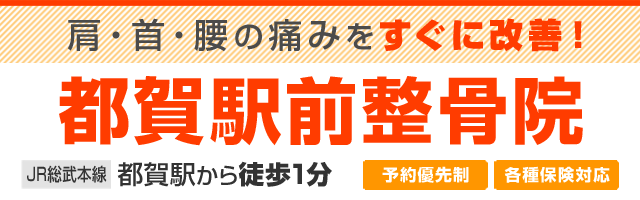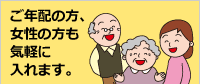オスグッド


こんなお悩みはありませんか?

膝下の痛みがあり、運動中や運動後に痛みが強くなる
膝下が腫れたり、膨らみや硬さを感じ、押すと痛みが強くなる
ジャンプや走るといった動作で痛みが増し、スポーツを継続することが困難である
運動を控えても痛みが完全に引かず、慢性化している
片側の膝だけでなく、両膝に症状が出ていて、日常生活やスポーツ活動に影響を及ぼしている
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッド病への対応ポイント
オスグッド病を軽減するためには、以下のポイントを理解し、適切に対応することが大切です。
休息と運動の制限
過度な運動や膝への負担は症状を悪化させる可能性があるため、痛みが強い場合はスポーツ活動を一時的に控えることが必要です。ただし、完全な安静ではなく、膝に負担をかけない範囲での軽いストレッチなどを取り入れることが望ましいです。
ストレッチと筋力トレーニング
大腿四頭筋やハムストリングスなどの筋肉が硬いと、膝にかかる負担が増します。これを防ぐために、適切なストレッチを行い、筋肉の柔軟性を保つことが大切です。また、体幹や下肢の筋力を強化するトレーニングも、膝への負担軽減に効果が期待できます。
アイシングと痛みの管理
運動後や痛みが強いときには、膝下を冷却することで炎症の軽減が期待できます。市販の鎮痛薬を使用する際には、必ず医師の指示を仰ぐようにしましょう。
サポーターやテーピングの活用
膝下にサポーターやテーピングを装着することで、運動時の膝への負担を軽減できます。正しい装着方法を学び、安全に活用することが重要です。
専門家による診察とフォローアップ
痛みが慢性化していたり、日常生活に支障をきたす場合には、整形外科医や理学療法士などの専門家に相談することをおすすめします。症状に応じた施術計画を立ててもらうことで、早期の軽減が期待できます。
オスグッド病は、成長期を過ぎると自然に落ち着くケースが多いとされていますが、早めの対応と継続的なケアが大切です。
症状の現れ方は?

オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)は、成長期の子どもやスポーツをしている若年層に多く見られる膝の症状です。主に、以下のような不調を訴える方が多くいらっしゃいます。
膝下の痛み
膝のお皿(膝蓋骨)の下にある「脛骨粗面」と呼ばれる部分に痛みが生じます。運動中や運動後に痛みが強くなるのが特徴です。
膝下の腫れや膨らみ
脛骨粗面が腫れ、膨らみや硬さを感じることがあります。触れた際に痛みが強まる場合もあります。
運動時の制限
ジャンプや走るといった動作を行うことで痛みが強くなり、スポーツの継続が難しくなることがあります。
休んでも続く慢性的な痛み
運動を控えても、痛みが完全には引かず、長期間続くこともあります。
片側または両側の症状
片側の膝だけでなく、両膝に症状が出ることもあり、日常生活や運動に影響が出ることがあります。
これらの症状は、成長期特有の骨や腱にかかる負担が関係しており、特に運動量の多い子どもたちにとって大きな悩みとなりやすいです。早めのケアや休養を心がけることが大切です。
その他の原因は?

オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)は、成長期の子どもやスポーツをしている若年層に多く見られる膝の症状です。主に、以下のような不調を訴える方が多くいらっしゃいます。
膝下の痛み
膝のお皿(膝蓋骨)の下にある「脛骨粗面」と呼ばれる部分に痛みが現れます。運動中や運動後に痛みが強くなるのが特徴です。
膝下の腫れや膨らみ
脛骨粗面が腫れ、膨らみや硬さを感じることがあります。触れることで痛みが強まることもあります。
運動時の制限
ジャンプや走るなどの動作をすると痛みが強まり、スポーツの継続が難しくなる場合があります。
休んでも続く慢性的な痛み
運動を控えても痛みが完全に引かず、慢性的に感じられることがあります。
片側または両側に現れる症状
片方の膝だけでなく、両膝に症状が出ることもあり、日常生活や運動に支障をきたすことがあります。
これらの症状は、成長期に特有の骨や腱への負担によって生じるものであり、特にスポーツを行う子どもたちにとっては大きな悩みのひとつです。膝への負担を避けるためには、適切なケアや休養を取り入れることが大切です。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッド病を放置すると、以下のような問題が後々発生する可能性があります。
慢性的な痛みの残存
オスグッド病は成長期が終わると軽減が期待されることが多いですが、放置すると症状が慢性化し、成長が終わっても膝下の痛みが残ることがあります。特に運動時や天候の変化に伴い、痛みが出ることがあります。
膝下の骨の変形
脛骨粗面が過度に突出してしまうことがあります。この膨らみは見た目に影響を与えるだけでなく、膝に直接的な負担をかけやすくなります。場合によっては、手術が必要となることもあります。
運動パフォーマンスの低下
膝の痛みをかばうことで、正しいフォームでの運動が難しくなり、他の部位(股関節や腰)に負担がかかります。その結果、怪我をしやすくなる可能性があります。
日常生活への支障
症状が悪化した場合、階段の上り下りやしゃがむ動作が困難になるなど、日常生活にも支障をきたすことがあります。
関節の機能障害
膝の過剰な使用や長期間の炎症が蓄積されると、膝関節の動きに制限が出る可能性があります。
適切な施術やケアを行わないと、成長期が終わった後も影響が残る可能性があるため、早期対応が重要です。
当院の施術方法について

当院にてオスグッド病の施術を行う際には、以下の項目を意識して施術を進めてまいります。
評価とアセスメント
患部の状態や疼痛の程度、筋肉の緊張度を評価します。関節の可動域や姿勢のバランスを確認し、原因となる要素を特定します。
手技療法
筋肉の緊張緩和
特に大腿四頭筋やハムストリングスの過緊張を解消するために手技療法を行い、身体の状態の軽減が期待されます。
関節の調整
膝関節や股関節の可動域を改善するため、適度なモビリゼーションを実施することが推奨されています。当院では骨盤剥がし、電気治療、鍼治療などを行い、関節の状態の軽減が期待されます。
テーピングとサポート
脛骨粗面への負担を軽減するため、適切なテーピング技術を用います。スポーツ活動時にはサポーターを推奨し、膝への負担を軽減することができます。
ストレッチ指導
大腿四頭筋、ハムストリングス、腸腰筋などのストレッチ方法を指導します。特に硬い筋肉がオスグッドの痛みを助長するため、柔軟性を高めることが重要です。また、より細かい場所の柔軟性を高めるために、当院では筋膜ストレッチを行う場合もあります。
筋力トレーニング
症状が軽減してきたら、下肢全体の筋力をバランスよく鍛えるトレーニングを指導します。特に臀部や体幹の安定性を高めることが効果的です。
冷温療法
急性期ではアイシングを用い、炎症を抑えることができます。慢性期では血流を促進するため、ホットパックや温熱療法を取り入れることが効果的です。
生活指導
症状が出やすい動作(しゃがむ、跳ぶなど)を避けるように指導します。
適切な靴の選択やスポーツ活動の頻度を見直すアドバイスも必要です。
注意点
症状が重い場合や痛みが長引く場合は、整形外科との連携を図り、医師の診断を仰ぐことも検討することが大切です。
柔道整復師として、患者さんの生活の質を向上させるために、段階的なアプローチが鍵となります。
改善していく上でのポイント

オスグッド病を軽減するためには、以下のポイントを理解し、適切に対処することが重要です。
休息と運動制限
過度な運動や膝への負担が症状を悪化させるため、痛みが強い場合はスポーツを一時的に休むことが必要です。ただし、完全な安静ではなく、軽いストレッチや膝に負担をかけない運動を取り入れることが推奨されます。
ストレッチと筋力トレーニング
大腿四頭筋やハムストリングスなどの筋肉が硬いと、膝に負担がかかりやすくなります。これを防ぐために、適切なストレッチを行い、筋肉の柔軟性を保つことが重要です。また、体幹や下肢の筋力を強化するトレーニングも有効です。
アイシングと痛みの管理
運動後や痛みが強いときは、膝下をアイシングして炎症を抑えましょう。必要に応じて市販の鎮痛薬を使用することもありますが、医師の指示を仰ぐべきです。
サポーターやテーピングの活用
膝下にサポーターやテーピングを巻くことで、運動中の負担を軽減することができます。正しい装着方法を学ぶことが重要です。
医師の診察とフォローアップ
痛みが慢性化したり、日常生活に支障が出る場合は、整形外科医や理学療法士の診察を受けましょう。症状に応じたリハビリプランを作成してもらうことが軽減への近道です。
オスグッド病は成長期が過ぎると自然に軽減することが多いですが、早期対応と適切なケアが重要です。
監修

都賀駅前整骨院 院長
資格:トレーニング指導者、中学校・高等学校第一種教員免許
(保健体育)、スポーツ施設管理師
出身地:三重県鈴鹿市
趣味・特技:野球、ドライブ、YouTube、観光