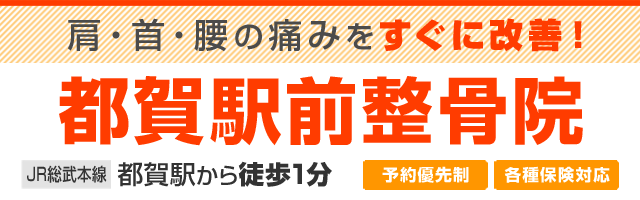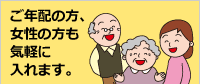巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

写真を撮ると猫背のように見えてしまう
姿勢が悪いと周りに言われたことがある
肩こりや首こりが慢性的につらい
呼吸が浅く、すぐに疲れを感じる
腕が上がりづらく、動かしにくさを感じる
頭痛や眼精疲労を感じることが多い
手や腕にしびれを感じることがある
四十肩・五十肩になりそうで不安
ストレートネックや猫背が気になっている
夜ぐっすり眠れない、なんとなく自律神経が乱れている気がする
巻き肩について知っておくべきこと

1. 姿勢が悪く見えてしまう
巻き肩になると、実際よりも猫背のような印象を与えてしまうことがあります。特に写真を撮るときや、鏡で姿勢を確認した際に気になりやすく、周囲から「姿勢が悪い」と指摘される方も少なくありません。
2. 肩こり・首こりがひどくなる
肩が前方に出た状態が続くと、首や肩まわりの筋肉に過度な負担がかかり、慢性的なこりや重だるさを感じやすくなります。
3. 呼吸が浅くなる
巻き肩になると胸が圧迫され、肋骨の動きが制限されるため、深い呼吸がしにくくなる傾向があります。その結果、疲れやすくなったり、集中力の低下を感じることがあります。
4. 腕が上がりにくくなる
肩関節の可動域が狭くなることで、腕をスムーズに上げる動作が難しくなり、日常動作やスポーツ動作に支障が出ることもあります。
5. 頭痛や眼精疲労が出やすくなる
首まわりの筋緊張や血流の悪化が影響し、頭痛や目の疲れ、違和感といった症状につながることもあります。
症状の現れ方は?

1. 肩こり・首こり
僧帽筋や肩甲挙筋など、肩まわりの筋肉が常に緊張した状態になり、慢性的な不快感が出やすくなります。
2. 頭痛やめまい
首の緊張によって血流が低下し、緊張性の頭痛やめまいといった不調を感じることがあります。
3. 手や腕のしびれ
巻き肩が原因で神経が圧迫され、腕や手にかけてしびれや違和感が出ることもあります。
4. 四十肩・五十肩のリスク増加
肩の可動域が制限されたまま生活を続けることで、関節に炎症が起こりやすくなり、四十肩・五十肩へとつながるケースもあります。
5. 自律神経の乱れ
巻き肩による胸郭の圧迫が、自律神経に影響を及ぼすことで、ストレスを感じやすくなったり、睡眠の質が低下したりすることもあります。
その他の原因は?

巻き肩は日常の姿勢や生活習慣の積み重ねによって引き起こされることが多いですが、それ以外にもさまざまな原因が関係しています。
まず、筋肉や骨格のアンバランスが大きな要因の一つです。肩を支える筋肉である僧帽筋や肩甲挙筋、大胸筋・小胸筋などが過度に緊張すると、肩甲骨や腕の動きに制限がかかり、肩が内側へ巻き込まれやすくなります。特にデスクワークやスマートフォンの操作などで、長時間前かがみになる姿勢が続くと、これらの筋肉に負担がかかり巻き肩を悪化させてしまいます。
また、胸郭の圧迫や肋骨の動きの制限も原因の一つです。胸が開きにくくなることで呼吸が浅くなり、酸素の供給が不十分となり、集中力の低下や疲労感、さらには自律神経の乱れを招くこともあります。
加えて、**骨格の歪み(骨盤のズレなど)**も巻き肩に影響します。骨盤の傾きや背骨のバランスが崩れると、自然と上半身の姿勢も乱れ、肩が前方に引っ張られやすくなります。これにより四十肩・五十肩のリスクが高まるほか、手や腕にしびれが出るケースもあります。
さらに、ストレスや睡眠不足などによる自律神経の乱れも無視できません。筋肉の緊張や血流障害を引き起こし、慢性的な肩こりや頭痛・眼精疲労を悪化させることがあります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩をそのまま放置しておくと、見た目の問題だけでなく、身体にさまざまな悪影響が現れてしまいます。
まず、姿勢が悪く見えることで、猫背に見えやすくなり、周囲から「姿勢が悪い」と指摘されることが増えます。写真や鏡で自分の姿を見ると気になりやすく、印象も老けて見られることがあります。
さらに、肩が前に出ることで首や肩の筋肉に負担がかかり、慢性的な肩こりや首こりがひどくなるほか、胸が圧迫されるため呼吸が浅くなりやすくなります。これにより疲れやすくなったり、集中力が落ちることもあります。
巻き肩によって肩関節の可動域が狭まるため、腕が上がりにくくなり、スポーツや日常生活の動作に支障をきたすこともあります。
また、首周りの筋肉が緊張して血流が悪くなるため、頭痛や眼精疲労を感じることもよくあります。
さらに進行すると、慢性的な筋肉の緊張により、手や腕のしびれが出ることや、肩の動きが悪くなり四十肩・五十肩のリスクが高まる場合もあります。加えて、胸郭の圧迫による自律神経の乱れが生じることで、ストレスや不眠の原因になることも少なくありません。
当院の施術方法について

整骨院では、巻き肩の改善に向けて以下のような治療を行います。
骨格・筋バランスの調整(手技療法)
巻き肩の主な原因は、大胸筋・小胸筋の過緊張と、僧帽筋下部や菱形筋の筋力低下にあります。手技療法により胸部の筋肉をほぐし、肩甲骨を正しい位置に誘導します。また、肩関節や頸椎の動きを改善し、可動域を広げる効果も期待できます。
筋膜リリース・ストレッチ
硬くなった筋膜をリリースして筋肉の柔軟性を回復します。特に大胸筋や小胸筋へのアプローチが重要で、施術と並行して患者様自身に行っていただくストレッチ指導も行います。
姿勢矯正・運動療法
肩甲骨の安定性を高めるために、僧帽筋下部・菱形筋・広背筋を鍛えるエクササイズを指導します。適切な運動により巻き肩の再発防止を目指します。
ハイボルテージ・EMS治療
電気刺激を用いて弱った筋肉を活性化します。特に肩甲骨内転に関わる筋肉を刺激し、正しい姿勢を維持しやすくします。
日常生活のアドバイス
デスクワーク時の姿勢改善や、肩甲骨を意識した生活習慣の提案を行い、根本的な改善をサポートします。
軽減していく上でのポイント

巻き肩を改善するには、筋肉の柔軟性向上、筋力強化、姿勢の意識、そして日常生活の改善が重要です。
筋肉の柔軟性を高める
巻き肩の原因となる大胸筋や小胸筋が硬くなり、肩が前に引っ張られています。まずはストレッチでこれらの筋肉をほぐしましょう。壁やストレッチポールを使った胸のストレッチを毎日行うことが効果的です。
背中の筋力を鍛える
肩甲骨を正しい位置に戻すために、僧帽筋下部・菱形筋・広背筋の筋力強化が必要です。軽いダンベルやチューブを使った「ローイング」や「肩甲骨寄せ」のエクササイズがおすすめです。
正しい姿勢を意識する
スマホやパソコン作業で猫背になりがちなので、こまめに姿勢を正す習慣をつけましょう。椅子に座るときは背もたれを活用し、肩を軽く後ろに引くことを意識することが大切です。
日常生活の改善
長時間のデスクワークでは1時間に1回肩甲骨を動かす、枕の高さを調整するなど、生活環境を見直しましょう。整体や整骨院での施術と併用して、これらの習慣を継続することで、巻き肩の根本改善につながります。
監修

都賀駅前整骨院 院長
資格:トレーニング指導者、中学校・高等学校第一種教員免許
(保健体育)、スポーツ施設管理師
出身地:三重県鈴鹿市
趣味・特技:野球、ドライブ、YouTube、観光